※本記事は医師による診断や治療を代替するものではありません。
医療機関での診察を受けつつ、自然療法を「自分の回復の選択肢のひとつ」として参考にしてください。
はじめに ― PMSは特別な人の病気ではありません
生理前にイライラしたり、気分が沈んだり、体がむくんだり…。
「気のせい」「私だけがおかしい」と思ってしまう方もいますが、PMSは決して特別な人にだけ起こるものではありません。むしろ、女性の約7割が程度の差はあれ不調を経験しているといわれています。
PMSとは(主流医学の視点)
PMS(月経前症候群)は、生理前3〜10日の黄体期にあらわれる心身の不調で、生理が始まると軽快または消失します。
医学的には、女性ホルモン(エストロゲンとプロゲステロン)の変動が原因のひとつとされており、このホルモン変動が脳の神経伝達物質や自律神経に影響することで、心身に症状が出ると考えられています。
PMSでよく見られる症状
からだの症状
- のぼせ
- 偏食や過食
- めまい
- からだがだるい(倦怠感)
- お腹・頭・腰の痛み
- むくみ
- お腹や乳房の張り
- 便秘
こころの症状
- 情緒が不安定になる
- イライラする
- 気分が落ち込む(抑うつ)
- 不安を感じる
- 不眠や眠気(睡眠障害)
- 集中力が低下する
幼少期の体験とPMS(月経前症候群)/PMDD(月経前不快気分障害)
PMSの原因は「ホルモン変動」と説明されることが一般的ですが、近年の研究ではそれだけでは説明できないことがわかってきました。
幼少期のストレス体験やトラウマが、大人になってからのPMSやPMDDの発症リスクを高めるという事実が報告されているのです。
たとえば、米国で行われた大規模な調査 では、幼少期に感情的な虐待を受けた女性は、受けなかった女性に比べて PMSを発症するリスクが約2.6倍に上昇することが確認されました。
身体的虐待でもリスクは約2倍に高まっており、この関連は喫煙や肥満といった生活習慣を調整しても残っていました(Nurses’ Health Study II/Harvard School of Public Health)。
また、日本で行われた研究でも、幼少期に身体的・感情的虐待を経験した女性ほど、PMSの症状が強く出やすいことが報告されています(東京医科歯科大学・名古屋市内クリニック共同研究)。特に、虐待の程度が強いほど症状が重くなる傾向が示されていました。

さらに、心理学的研究では、不安を感じやすい性格や、自分を責めやすい性格といった傾向を持つ人ほど、PMSやPMDDの症状が重くなりやすいことも分かっています(Massachusetts General Hospital Center for Women’s Mental Health ほか)。
このように、PMSは単なるホルモンの乱れではなく、幼少期の体験・性格的傾向・ストレス環境が積み重なって現れる「心と体の両面の症状」と考えることができます。
症状の背景に「未処理の感情や体験」があることを理解すると、自然療法でのアプローチ――つまり「症状を抑え込むのではなく、そのメッセージを受け取ること」がより深い意味を持つのです。
では、PMSの症状を「敵」ではなく「体からのメッセージ」として捉えたら、どんな可能性が見えてくるのでしょうか。次に、自然療法の視点から見ていきましょう。
自然療法の視点 ― 症状は敵ではなく、メッセージ
自然療法では、PMS/PMDDの症状を単なる「不快な不調」とは見ません。
それは 「体と心からのメッセージ」 であり、私たちが気づくべきサインと捉えます。
2つの現れ方
- 浮上タイプ
-
幼少期に抑圧されてきた感情(怒り、悲しみ、不安)が、月経前というホルモンの変動期に表面化してくるケース。 普段は我慢できても、この時期には心の奥にしまい込んだ気持ちが顔を出し、「本当はこう感じていた」という声に出会うきっかけになります。
- 身体化タイプ
-
言葉や感情として出せない思いが、頭痛・腹痛・乳房の張り・むくみなど身体症状として現れるケース。
「体が代わりに語っている」と考えると、症状はただの敵ではなく、自分の心身を見つめ直す入り口になります。
なぜ「月経前」に出るのか?
ホルモンが変動する時期は、自律神経や感情のバランスも揺らぎやすくなります。
そのタイミングで抑えてきた感情が浮かび上がり、身体症状として表れやすいのです。
自然療法の視点では、これは「心と体の調整のプロセス」であり、症状を通して“未消化の体験”や“気づかれていない感情”にアクセスできるチャンスと考えます。
セルフケアの意味が変わる
「なぜこのタイミングでこの症状が出るのか」に気づくことは、セルフケアを単なる対処法ではなく、自分の内面に寄り添う実践へと変えてくれます。
アロマやハーブ、レメディ、食事の工夫などの自然療法を取り入れるときも、「症状を消す」のではなく「体が伝えたいことを聞き取る」姿勢が大切です。

私のセッションでできること
感情との対話(カウンセリング・探求)
幼少期の体験や性格傾向を一緒に振り返り、「どのように感情を抑え込んできたか」「それが今の症状とどうつながっているか」を整理します。
感情を安全に言葉にできる場を持つことで、孤独感が和らぎ、症状に意味を見いだす力が育ちます。
ホメオパシー・レメディー
ホメオパシーのレメディーは、エネルギー化された情報として「抑圧された未消化の感情」に共振し、無意識の底に眠っていた感情を優しく浮上させます。
また、薬草療法(マザーチンクチャーなど)弱った臓器や自律神経の働きをサポートし、感情が滞りなく流れるための身体的な土台を整えます。「心に働きかけるレメディー」と「体を整えるレメディー」の両輪で、深いレベルから回復力を引き出します。
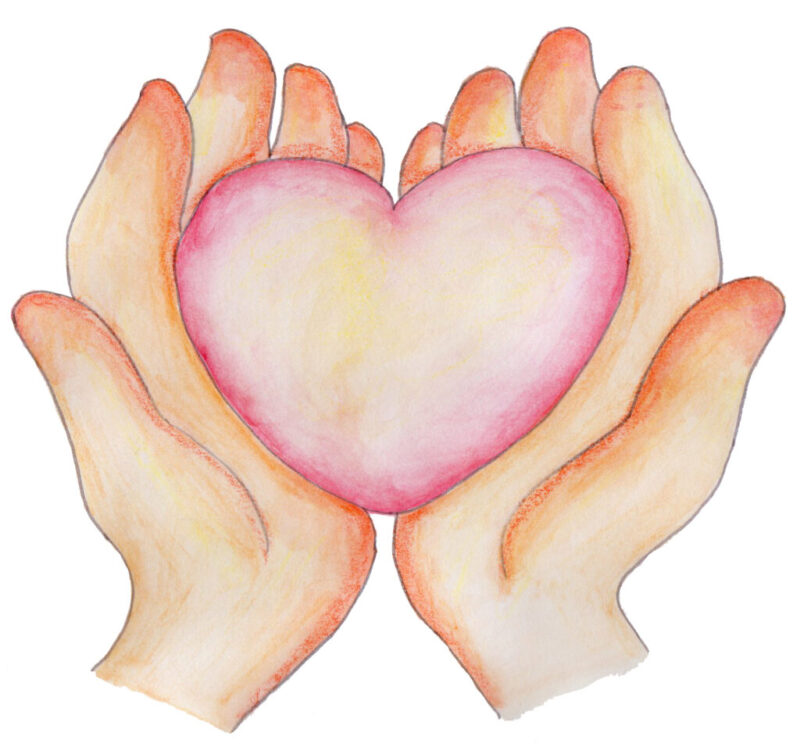
ライフスタイル調整とセルフケア
栄養・休養・リラクセーション・職場や家庭環境の調整など、日常生活に落とし込める具体的な方法をご提案します。長年の習慣や無意識の反応を見直すことで、「月経前のつらさに振り回される生活」から「自分のリズムを理解し活かす生活」へと変化していけます。
最後に ― あなたへのメッセージ
PMSやPMDDのつらさは、決して「あなたが弱いから」起きているのではありません。
それはむしろ、あなたの体と心が精一杯メッセージを送っている証拠です。
「もう少し自分をいたわってほしい」
「抑えてきた気持ちに耳を傾けてほしい」
症状はそう語りかけているのかもしれません。
自然療法は、その声に耳を澄ませ、自分自身とより深くつながるためのサポートになります。
セルフケアの一歩を踏み出すことは、自分を大切にする第一歩です。
あなたの心と体には、本来、回復しようとする力が必ず備わっています。
その力を信じて、少しずつでも自分に優しい選択を重ねていきましょう。

よくある質問(Q&A)
Q PMSとPMDDはどう違うのですか?
A 主流医学では、PMSは「生理前に心身に起こる幅広い不調」を指します。その中でも特に精神症状(強い抑うつ感、怒り、感情のコントロール困難)が重く、日常生活に支障をきたす場合は医師によってPMDDと診断されます。
自然療法の視点では「診断名」ではなく、症状が心と体からのメッセージとして現れていると考えます。
PMSでは「日常の中で抑えてきた感情や疲労」が比較的軽度に出てきやすく、PMDDのように強い精神症状を伴う場合は「抑圧された感情やストレスがより深いレベルで噴き出している状態」とも捉えられます。
そのため自然療法では、症状を「敵」とみなすのではなく、その奥にある感情や心身の声をどう受け止めるかを大切にしています。
Q どうして人によって症状の出方が違うのですか?
A 主流医学的には、ホルモンの変動の受け止め方が個人差を生むとされます。
一方で、自然療法では「性格傾向」「ストレス環境」「幼少期の体験」が大きく影響すると考えます。
例えば、我慢強い人は感情を体に閉じ込めて頭痛やむくみになりやすい、といったパターンです。
Q 薬を使わずに改善できますか?
A 主流医学では、PMSの頭痛には鎮痛薬、不安や抑うつには抗不安薬・抗うつ薬、重症例には低用量ピルなどが用いられるようです。いずれも「症状を抑える」ための対処療法といえます。
一方で、薬を使わなくても セルフケアや自然療法で症状が軽減する人は少なくありません。
栄養・睡眠・運動・感情表現の工夫によって、ホルモン変動の影響を受けにくい心身の土台を整えることができます。
大切なのは「薬を使うか/使わないか」ではなく、自分に合った方法で心身の回復力を引き出すことです。
Q 月によってPMSの重さが違うのですが、なぜでしょうか?
A はい、PMSの症状は毎月同じとは限らず、その重さには波があります。
医学的には、ホルモンの変動は一定のリズムで起きていますが、その影響の受け方は ストレス・睡眠・食事・体調の積み重ね によって変わると考えられています。
たとえば「今月は仕事で強いストレスが続いた」「睡眠不足が重なった」といった要因が、症状をより強く感じさせることがあります。
自然療法の視点では、症状の重さは 心身がどれだけ我慢を抱え込んできたか とも関係しています。
「何を我慢してきたか」「どんなことで自分を責めてきたか」「誰かから責められているように感じたか」を振り返ると、症状が教えてくれているメッセージに気づけることがあります。
つまり、PMSの重さの変動は「その月の心と体の状態を映し出すバロメーター」とも言えるのです。
Q パートナーや家族にどう説明すればいいですか?
A PMSは「性格の問題」でも「気の持ちよう」でもなく、ホルモンのリズムに伴って周期的に起こる心身の変化です。
それを周囲に理解してもらえるだけで、つらさは和らぎます。
逆に、「わかってもらえない」「一人で抱え込むしかない」という孤独感が強まると、PMS/PMDDの症状はさらに深刻になってしまいます。
説明のコツ
1)具体的に伝える:「生理の前の一週間は頭痛とイライラが強くなる」など、症状とタイミングをはっきり言葉にする
2)お願いをシンプルにする:「この時期は家事を少し手伝ってもらえると助かる」「仕事の締切は余裕を持たせたい」など具体的に頼む
3)相手を責めずに伝える:「あなたのせいでつらい」ではなく「この時期は体の調子が不安定だから協力してほしい」と伝える
周囲に理解されることで、孤独感が軽減され、安心して過ごせる環境につながります。
家族やパートナーも「どう関わっていいかわからない」と不安を抱えていることが多いため、説明することでお互いの安心感が高まります。
もし『一歩踏み出してみようかな』と感じられたら、相談会をご利用ください。
無理に変えるのではなく、あなたのペースで歩めるよう伴走いたします。
※ここでお伝えする内容は診断や治療を代替するものではありません。
医師の診断や治療を受けながら、その補完的なケアとして自然療法をご活用ください。
あなたの心と体には、本来の回復力が必ず備わっています。


「他の方の事例も知りたい」と思われた方は【症例ケース】からご覧いただけます。
「自分や家族の状況に合わせたサポートを受けたい」と感じた方は【自然療法のご相談はこちら】からどうぞ。

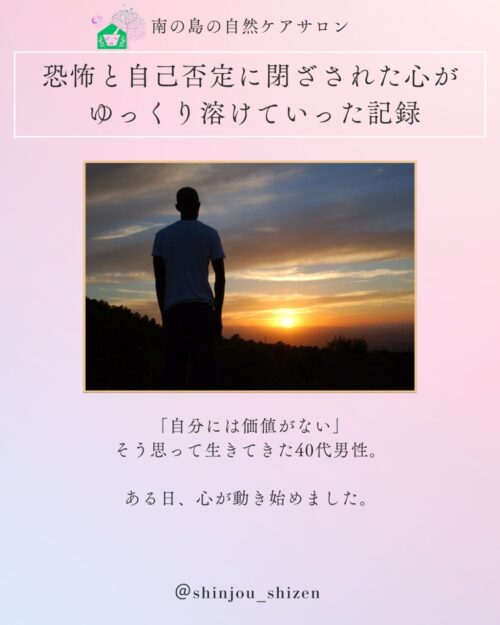






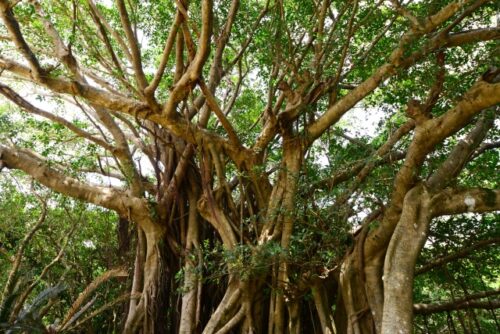
コメント