あなたやあなたの家族に「柔軟剤の匂いで気分が悪くなった」方はいませんか?
今、学校という閉鎖的な空間で、“香り”が子どもたちの健康を脅かしています。
日本臨床環境医学会が行った2024年度の調査によると、小中学生の約1割が「香害」による体調不良を経験。
頭痛、吐き気、倦怠感、微熱などの症状があり、中には不登校にまで追い込まれるケースも報告されています。
教室に漂う「見えない化学物質」

柔軟剤や香水、消臭スプレーなどに含まれる香料の多くは、石油由来の合成香料や揮発性有機化合物(VOC)です。
香りを長く残すために使われるマイクロカプセル技術は、衣服や髪に付着した化学物質を少しずつ空気中に放出し続けます。
これらの香り分子は、鼻の奥の嗅球(きゅうきゅう)を刺激し、脳の感情中枢や自律神経に直接作用します。
心地よいはずの香りが、ある人には頭痛や息苦しさ、集中力低下を引き起こす。
それが今、学校現場で起きている現実です。
世界はすでに「香りの安全」へ動いている
ヨーロッパでは、香料による皮膚炎やアレルギーが社会問題化し、2005年からアレルゲンとなる香料26物質の表示義務が導入されました。
日本では今も「香料」と一括表示が認められ、どんな成分が使われているのか、消費者が知る手段はありません。
香りの文化が進む一方で、「香りの安全」はまだ議論の途上にあります。
自然療法的にできること
ニオイで気分が悪くなるのは、気のせいではなく、神経・ホルモン・免疫のバランスが乱れたサインでもあります。
特に繊細な嗅覚を持つ方が影響を受けやすいと言われます。
自然療法では、過敏に反応する身体を「疲れたセンサー」と捉え、感覚を静めることから始めます。
1)コーヒー豆で嗅覚をリセットする
強い香料を嗅ぎ続けると、嗅覚が麻痺して何が自然で何が刺激か判断できなくなります。
そんなとき、コーヒー豆の香りを軽く嗅ぐと嗅覚がリセットされる事が知られています。
コーヒーの芳香分子が嗅球を一度“中立状態”に戻してくれるのです。
香り疲れを感じたとき、机の上に少量のコーヒー豆を置き、鼻を近づけて深呼吸をひとつ。
五感が一瞬でリセットされ、頭の重さや心のざわめきがすっと鎮まるのを感じるでしょう。


2)緑茶のタオルで空気を中和する
香りの強い空間にいるときは、緑茶でタオルを湿らせ、軽く絞って振ってみましょう。
これは古くから伝わる自然の脱臭法であり、緑茶に含まれるカテキンやポリフェノールが臭気成分を吸着・中和してくれます。
タオルをゆっくり回すと、茶の分子が空気中の化学物質をつかまえ、その場の空気をやわらかく整えてくれるのです。
化学的に「消す」のではなく、過剰な刺激を“地の香り”で中庸に戻す働きがあります。
3)ホメオパシー的サポート
フォスフォラス(Phos):光・音・匂いなど五感に敏感な人に
ナックスボミカ(Nux-v):刺激過多・神経過敏な人に

香りと共に生きるために

香りは、本来、自然が生み出す生命の情報でした。
けれど、現代文明の中で暮らす我々は呼吸のたびに人工的な香りの中で暮らしています。
“いい香り”なはずなのに、心地よく感じられないとき、それは身体が「もう休ませて」と教えているサインかもしれません。
香りを控えることは、誰かの苦しみを減らすだけでなく、自分の呼吸と感覚を取り戻すことにもつながります。
静かな香りのない空気が、子どもたちの未来と、私たちの神経をやさしく守ってくれるのです。
自然療法での【症例ケース】は以下からご覧いただけます。
「自分や家族の状況に合わせたサポートを受けたい」と感じた方は【自然療法のご相談はこちら】から
参考記事

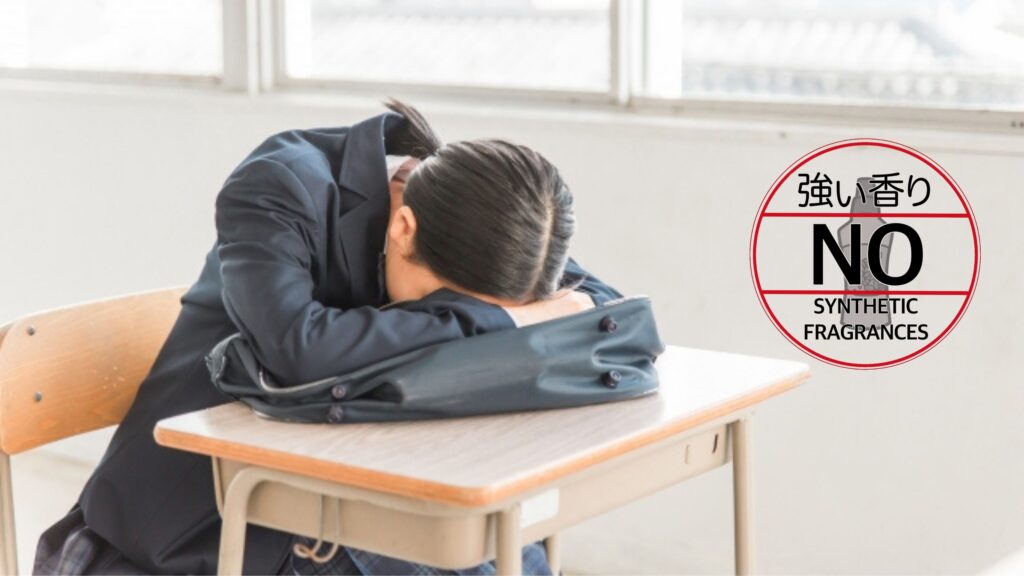
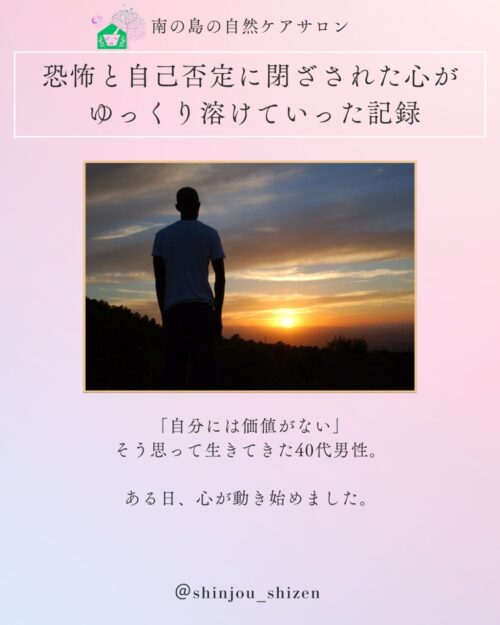






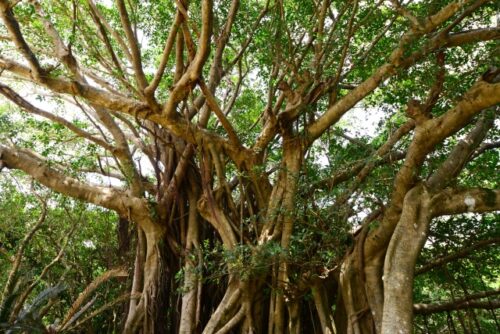
コメント