朝、コンビニやカフェで手に取る一杯のコーヒー。忙しい日常の中で欠かせない、ほっとする時間という方は多いと思います。でも、その紙コップの中に「目に見えない粒子」が溶け出しているとしたら――。
見えないプラスチックを飲んでいる?
インド工科大学カラグプル校の研究チームは、市販の紙コップ5種類に85〜90℃の熱湯を注ぎ、15分間放置するという実験を行いました。
その結果、紙コップ1杯(100 ml)の湯の中に、約2万5000個のマイクロプラスチック粒子が確認されたと報告されています。
これらの紙コップの多くは、内側に高密度ポリエチレン(HDPE)フィルムがコーティングされており、熱湯を注ぐことでその膜が劣化し、微細なプラスチック粒子が飲料中に放出されてしまうのです。
さらに、1ミクロン未満の超微細粒子(サブミクロンサイズ)も数多く検出されており、飲料中に溶け込んだイオン(フッ化物・塩化物・硫酸塩・硝酸塩など)も「紙コップ由来」である可能性が高いとされています。

子ども用のコップや食器も安心できない?

この問題は“大人の紙コップ”に限った話ではありません。
子ども用のコップ・食器(軽くて割れにくいプラスチック製)も、同様のリスクをはらんでいるという指摘が増えています。
例えば、乳幼児・幼児を対象にしたレビューでは、哺乳びんやプラスチック製カップ・食器・おもちゃなどがマイクロプラスチック(MP)曝露の重要な源であると報告されています。
プラスチック製のコップや皿を熱湯や電子レンジで加熱したり、繰り返し使用・摩耗・傷がついたりすると、微粒子の放出量が増える可能性が高いという実験的データも示唆されています。
つまり、「割れにくくて安心」という理由だけで安易に選ばれた子ども用食器にも、熱・時間・使用状況によっては“見えない粒子の負担”が潜んでいるのです。
体への影響は?
現時点ではマイクロプラスチックが直接どのような健康被害を引き起こすか、すべてが明らかになっているわけではありません。
しかし、研究者らは「マイクロプラスチックは有害な重金属(パラジウム・クロム・カドミウムなど)を運ぶ媒体となる可能性がある」と指摘しています。
子どもは体重あたりの飲料・食器からの取り込み量が大人より相対的に高く、成長期という観点からも慎重な対応が求められます。

知っているのに、なぜやめられない?
こうした情報を「知っている」人は多いでしょう。
けれど、知っているはずなのに、私たちはまた紙コップを使い、割れにくいプラスチック食器を選んでしまう。
その理由は簡単です。忙しい朝、子どもとの食事、職場、シーンにおいて「便利で手軽」が優先されるから。
でも、知っていることと実際に選ぶことの間には、深い溝があります。
「便利=安全」と思い込んでしまうその根底に、意識的な選び方が欠けているのです。
では、どうすればいいのか?
特別なことをする必要はありません。ほんの少しの“選び方のシフト”で、体への負担を減らすことができます。

1)マイマグ・耐熱素材の食器を使う
子ども用でも、陶器・ガラス・ステンレス製を選ぶことで、プラスチック由来の微粒子リスクを下げることができます。
2)プラスチック製コップ・食器を使う場合は“熱湯や電子レンジ加熱を避ける”
傷・変形・変色が見られたプラスチック製食器は早めに交換を検討する
使用年数・傷・摩耗が進むと、素材劣化による微粒子放出リスクは高まります。
3)「使い捨て」「軽くて手軽」の選択を見直す
子どもとの日常において、“軽くて割れにくい”だけでなく「何でできているか」「どんな場面に使うか」を意識することが、健康という資産を守る一歩です。
健康は、最大の資産
経済的に豊かでなくても、健康である人は大きな資産を持っているのです。
健康を守るということは、見過ごされがちな“資産防衛”。
そしてそれは、特別なサプリメントや高価な治療よりも、「何を選び、何を避けるか」という小さな判断の積み重ねから始まります。
知ることは、怖がることではありません。
気づいた瞬間から、選び方が変わる。
それが、体と地球の両方を癒す最初の一歩です。
今日の一杯を飲むとき、そしてお子さんのコップを選ぶとき、あなたはどんな素材を手にしていますか?

自然療法での【症例ケース】は以下からご覧いただけます。
「自分や家族の状況に合わせたサポートを受けたい」と感じた方は【自然療法のご相談はこちら】から
参考記事


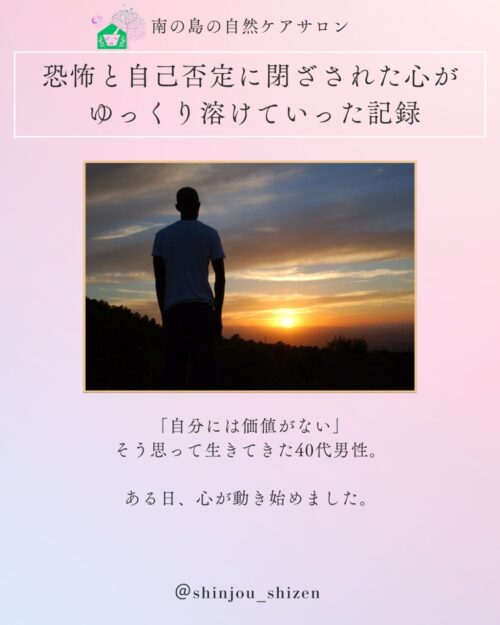






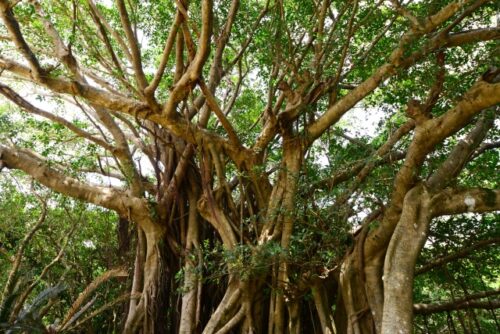
コメント